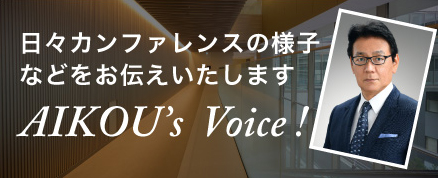AIKOU’s voice
- トップページ
- AIKOU’s voice
- 朝カンファレンス
朝カンファレンス
皆さん、おはようございます。毎日患者さんのために、産婦人科学講座のために、そして世界の女性と子どもを幸せにするために頑張ってくださり、ありがとうございます。本日は岡本教授に代わり、岸がお話させていただきます。
今回は日本の生殖補助医療に関する法案についての情報提供です。
御存知の方もいらっしゃるかと思いますが、現在行われている第217回国会に、提供型特定生殖補助医療法案が提出されました。これは、夫婦以外の第三者から精子や卵子の提供を受けて不妊治療を行う際のルールを定める法案となっています。また、こうした配偶子を用いた治療の結果として生まれた子の出自を知る権利についても、初めてその一部を認める内容となっています。
現在、日本で第三者の配偶子を用いる医療として認められているのは、明確にAIDのみです。長年、日本には生殖補助医療に関する法律はなく、日本産科婦人科学会がその方針を会告として定め、それに沿って治療が提供されてきました。学会としては、20年以上前から国によるルール作りを求めて来ており、第三者配偶子を用いた治療により生まれた子の親子関係については、令和4年に生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律として定められていますが、今回ようやく第三者配偶子を用いた生殖医療自体に関する法案が提出されました。
内容としては
・第三者ドナーから精子・卵子を集める医療機関
・不妊治療を実施する医療機関
・その間で精子や卵子を斡旋する機関
を定め、それぞれ認定や許可を受けた施設のみでの実施を許可するとしています。
この3つの機能を同一の医療機関が担うこともできますが、営利目的として行うことは認められていません。
実施される医療行為としては、AIDのみではなく提供卵子・精子を用いた体外受精が可能になりますが、代理出産は認められていません。また、この治療を受けることができる対象は法律婚の夫婦のみで、現在保険で行われている生殖補助医療の事実婚の夫婦も対象としている点とは異なっています。
そのほか学会の会告として行われていた場合と大きく異なるのは、罰則の規定があることです。違反内容により、懲役刑や罰金刑が定められています。
配偶子を提供したドナーの情報は国立成育医療センターで100年間保管されることとなっており、生まれた子が成人したあとに求めれば、個人の特定につながらない情報の一部(身長、年齢、血液型等)は開示されますが、それ以上の情報の開示にはドナーの同意が必要となります。
この法案が国会を通るかどうかはまだ分かりませんが、長らく学会が求めてきたものがようやく形になろうとしているものですし、法律となるとこれまでとはその重みが全く異なるものとなりますので、その採否についてはひき続き動向を見守っていきたいと思います。皆さんも良かったら、ちょっと注意してみてください。
それでは今週もよろしくお願いいたします。